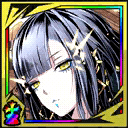QUESTS EP:扉の先へ:聖神
扉の先へ:聖神Ⅰ
-
神界に模されて創られていた理想郷アヴァロン。その最奥の玉座にひとり腰をかけていた聖神アーサー。彼は終わる世界を見ながら、なにを考えているのだろうか。なにを想っているのだろうか。彼の心を知るのは彼ひとり。そして、最後の幕は上がる。
-
思い返せば、それは短い道のりだった。そして、長い道のりだった。始まりは雪降る聖なる夜。ふたりの優しさが生んだ親友との出会い。そして、その出会いが決定付けた彼の生きる道。選ばれた王道。王たるものは民に弱さを見せることは出来ない。
-
やがて王は闇へと堕ちた。堕ちようとも、王が見つめていた希望。その希望がもたらしたのは神への道。そう、神たるものは王に弱さを見せることは出来ない。だから俺は決して立ち止まることは出来ないんだ。それが、神という存在なのだから。
-
神は王へ、民へ恵みを与えると同時に、必ず試練を与える。それが正しいのか、間違っているのか。議論の余地はない。それが神の存在意義なのだから。イマの世界へ与える試練。そして、代わりに与えられる恵みは生まれ変わる世界。それが世界の理。
-
神話の時代から、世界は常に崩壊と再生を繰り返していた。そこに疑問を抱く神々は少なかった。そう、今回の世界が生まれ、イマのために戦う者たちが現れるまでは。だが、なぜ今回の世界はその輪廻の歯車から外れようとしているのだろうか。
扉の先へ:聖神Ⅱ
-
数多の因果が絡まりあい、生まれてしまった禁忌の子。そして、沢山の愛情に包まれながら、生きてしまった禁忌の子。だからこそ、その子だけは理の外側にいた。そうさ、俺に出来ることは、もう少ししか残されていないんだ。それは、なんのためか。
-
それとも、誰のためか。ただ、アーサーは終わりゆく世界を見つめながら、自分のやるべきことを見据えていた。どうか、世界が平和でありますように。それは、いつか彼が抱いていた希望。どうか、世界に幸せが溢れますように。それもまた、希望。
-
少しずつ、近づく足音。その音は7つだった。ようやく、あいつらが来たみたいだ。真剣な表情だったアーサーの口角が少し上がる。彼らは、希望だろうか、絶望だろうか。そう言葉を口にしたのは、音もなく現れた創醒の聖者。さぁ、どっちだろうな。
-
世界の終わりというのは、いつも悲しいものだ。無表情のまま、似合わない言葉を口にした創醒の聖者。君はいま、どちらを見つめている。アーサーのほうを向くことなく、問いかけたのも創醒の聖者だった。俺が見たい景色は、昔もイマも変わらない。
-
そして、創醒の聖者は続けた。幾重にも連なった悲しみの連鎖、それを終わらせることなど出来はしない。だが、それでも君が望むのなら、その世界を見せよう。映し出された世界。これが君の理想とした世界だよ。そこにはひとつの扉が浮かんでいた。
扉の先へ:聖神Ⅲ
-
ただ、なにもない空間。浮かんでいた扉。その扉は瞳にも似ていた。そして、その瞳にはなにも映ることはない。これが、私たち聖なる扉<ディバインゲート>が見つめる世界だ。私たちの瞳には、決してなにも映らない。世界の歩みは止まるのだから。
-
悲しみの連鎖が途切れること、それは世界の進歩を止めるに等しいこと。だから、その世界にはなにも存在していない。その世界は絶えるのだから。だからこそ、私たちは世界を創り直す必要がある。そう、これは生きとし生ける命のためなのだから。
-
そうだな、俺もそうだと思う。そう答えたアーサー。いや、思っていた、と言ったほうが適切かもしれないな。そう言い直したアーサー。いいや、いまさらなにを言っても変わりはしない。そう続けたアーサー。君はいったい、なにを思っているんだい。
-
俺は俺の、成すべきことをするだけさ。それが、この世界の終わりだと知ってのことか。あぁ、それでも俺は構わない。たとえ世界が果てようと、それでも新しい芽は生まれる。やがて、花は開く。俺はその可能性を信じる。それが俺の見た希望だ。
-
そんなことのために、君は自分を犠牲にするというのかい。アーサーから抜け落ちた感情。失われていた自己愛、残されていた慈愛。そう、それこそが世界の理の外側の存在であるがゆえ。ようやくわかったよ。君という存在は、世界に存在していない。
扉の先へ:聖神Ⅳ
-
かつて、聖王アーサーという存在は間違いなく世界の中心に存在していた。だが、その心はその世界には存在しているようで、存在していなかった。創醒の聖者が世界そのものを形創るのだとしたら、アーサーが形創ろうとしていたのは、世界の外側。
-
理の外側、そう、唯一の世界の外側の存在であるアーサー。彼が成すべきこと。それは世界の外側から、世界の理に干渉すること。すなわち、世界の内側を司る聖なる扉への干渉。消滅。いまの俺なら、それが出来るだろう。そう、俺は成すべきことを。
-
かつて、堕ちし王が選んだ神への道。それは決して絶望の道ではなく、希望の道だった。やはり、この世界にディバインゲートなんて必要ないんだ。だからこそ、俺がこの繰り返された崩壊と再生の歴史に終止符を打とう。イマを生きる命をかけて。
-
入口が存在するから出口が存在するかのように、内側が存在したからこそ存在した外側。ならば、私は君を喰らうことで、完璧な存在になれるのだろう。そして、俺はその言葉をそのまま返させてもらう。そう、共にひとつになろう。聖なる扉として―。
-
アカネたちが辿り着いた王の間への入口。重い扉から溢れ出した金色の瘴気。そう、この奥にアーサーがいる。意を決して開かれた扉。置かれていた玉座。たった「ひとり」の人影。ようこそ、聖なる扉の間へ。君たちを歓迎しよう、そう―この私が。