STORIES 2017年3月14日のストーリー
この日に実装されたストーリーの一覧です。
-
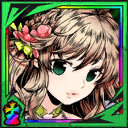 世界の決定:8人目
世界の決定:8人目
♯01 世界の決定:8人目キミみたいな綺麗な女性の相手が出来て嬉しいよ。ポストルがしならせた蛇腹剣。私は嬉しくないわ、いまどきロン毛の男なんて気持ち悪いわよ。ヒルダが引いた弓。ご忠告、ありがとう。一瞬にして詰められた距離。素直なキミのことが気に入ったよ。 -
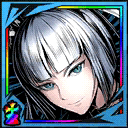 世界の決定:8人目
世界の決定:8人目
♯02 世界の決定:8人目誰かみたいなこと言わないで。慌てて身を翻したヒルダは距離をとる。ポストルの蛇腹剣が届かない場所へと。だが、それでも伸び続ける刃。ヒルダの放つ矢はことごとく避けられ、傷を与えることは出来なかった。まだ、逃げる力が残っているのかな。 -
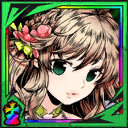 世界の決定:8人目
世界の決定:8人目
♯03 世界の決定:8人目立ち止まったヒルダ。この声が届きますように。天へ放つ想いを乗せた矢。王への遺言かな。歩み寄るポストル。許して、私の負けよ。ポストルへと抱きつくヒルダ。なんて、私は可愛い女じゃないの。そして天へと放った矢は涙のように降り注いだ。 -
 世界の決定:8人目・回想
世界の決定:8人目・回想
♯01 世界の決定:8人目・回想アーサーたちは警備局と現場が重なることが多々あった。そんな重なった現場にいた警備局員の中にヒルダがいた。誰よりも文句を並べながら、誰よりも働いていたヒルダ。アーサーの瞳には、どこかヒルダがひとりで戦っているように映ったのだった。 -
 世界の決定:8人目・回想
世界の決定:8人目・回想
♯02 世界の決定:8人目・回想アーサーへ臆することなく不満を口にしたヒルダ。あんたの部署の男ども、がさつ過ぎんの。あぁ、うちの自慢のクズ共だ。地位が上がるにつれ、イエスしか言わない存在が増えたアーサーにとっては心地よかった。オマエに、相応しい居場所がある。 -
 世界の決定:8人目・回想
世界の決定:8人目・回想
♯03 世界の決定:8人目・回想もう、あんたにはなにを言っても無駄なのね。そして、異動と共にケイのコードネームが与えられたヒルダ。口の悪さは相変わらずだが誰よりも丁寧に仕事をこなしていた。口の悪さによる喧嘩は一部ではあるものの、それすらも微笑ましい日常だった。 -
 世界の決定:8人目・回想
世界の決定:8人目・回想
♯04 世界の決定:8人目・回想また、ケイの悪口はいつも的を得ていた。鋭い洞察力と少しの思いやり、そして多くの自己主張が心の真ん中へと突き刺さる。君を選んだことに、間違いはなかった。そう、アーサーが求めていたのは、ただの上司と部下の関係ではなかったのだから。 -
 世界の決定:8人目・回想
世界の決定:8人目・回想
♯05 世界の決定:8人目・回想口を開けば食事の文句やマナーの文句ばかり。だが、そんないつものケイの悪口も、最後の晩餐へ色を添えていた。もう、あんたたちといると、本当に疲れるわ。まぁ、飽きないけどね。ケイは肯定した。この円卓こそが自分の居場所だったんだ、と。 -
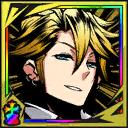 世界の決定:9人目・回想
世界の決定:9人目・回想
♯01 世界の決定:9人目・回想ライルという名の孤児がいた。ヴィヴィアンにとって、その孤児は都合の良い存在だった。そして、ライルはヴィヴィアンに引き取られたとき、幼くして運命が決定づけられていた。そう、このときから、ライルはアーサーという鎖に縛られていた。 -
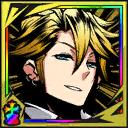 世界の決定:9人目・回想
世界の決定:9人目・回想
♯02 世界の決定:9人目・回想それでも、ヴィヴィアンは愛を込めて育てた。だが思春期のライルにとって、本当の両親がいないというのは道を逸れるのに十分な理由だった。そして時は流れ、喧嘩、酒、女に明け暮れる毎日。そんな荒くれ者の噂がアーサーへと届けられたのだった。 -
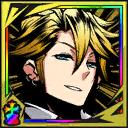 世界の決定:9人目・回想
世界の決定:9人目・回想
♯03 世界の決定:9人目・回想常界の路地裏、出会ってしまったふたり。そして交された約束。いつか俺がオマエを殺す。あぁ、それまで俺は、誰にも殺されやしない。与えられたランスロットというコードネーム。こうして、危険をはらんだ9人目の円卓の騎士が生まれたのだった。 -
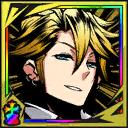 世界の決定:9人目・回想
世界の決定:9人目・回想
♯04 世界の決定:9人目・回想ランスロットは信じていた。アーサーの大それた言葉に嘘偽りはないと。だからこそランスロットはアーサーに従った。そして知ることになる自分の存在理由。幼き日から自分を縛り続けていた鎖。運命。コイツを殺すのは、俺じゃなきゃダメなんだ。 -
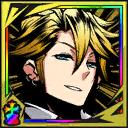 世界の決定:9人目・回想
世界の決定:9人目・回想
♯05 世界の決定:9人目・回想ヴィヴィアンとふたりで生きてきたランスロットにも居場所が生まれた。馴れ馴れしく接してくる同世代の同僚。無駄につっかかってくる生意気な弟分。その他大勢の仲間。アーサーを殺すと想いながらも、かけがえのない仲間たちが生まれたのだった。