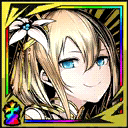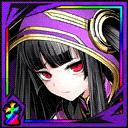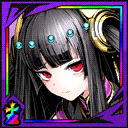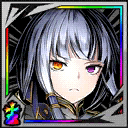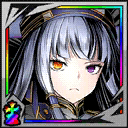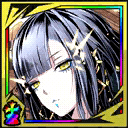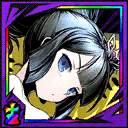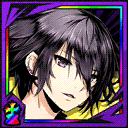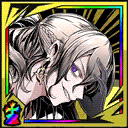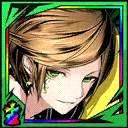王として創られた男は、そのすべてが個の為に捧げられていた。そう、だって俺はその為に生まれたのだから。だが、そんなオベロンのことを、王でありながらも、友として接してくれたふたりの友がいた。迫る決断の日と、今も出せない答え。それは王でありながら、友を手にしてしまったがゆえの弱さと優しさだった。
王は個でなく、全である。それは魔王ヴラドが貫いた覚悟。そうさ、オレは友である前に、王なんだ。自ら下した苦渋の決断。民を守る為に、友を殺す。だが、どうしてだろう。天界への進軍前夜、真っ赤な月が滲む夜。王の瞳に溢れた想い。頬を伝うことはオレが許さない。そして魔王は、固く瞳を閉ざしたのだった。
あぁ、再び目醒めの刻が訪れてしまったのですね。アルルは天へ祈りを捧げる。どうして、みな争いを繰り返すのでしょうか。それは繰り返された聖戦を意味していた。あのときも、あのお方は争いを止める為に力を貸したに過ぎないというのに。創醒の聖者の血がもたらしたのは、かつての聖戦の終結だった。
ようやく、見つけた。常界の始まりの地、ただ天へと祈りを捧げる聖巫女アルルの元に現れたのは炎咎甲士だった。よく、この場所がわかりましたね。友達が力を貸してくれた。そして、彼女がここに連れてきてくれたんだ。彼のとなりに寄り添っていたのは神威狐。だから俺は、俺のすべきことをするんだ。
神に逆らうなど、愚かな行為だ。ナルルはただ悲劇を傍観していた。どうして、父であり、母であるあのお方を悲しませるようなことを。彼女の役割もまた、創醒の聖者の為にあった。再び訪れようとしている目醒めの刻。その刻が訪れてしまえば、すべてのものごとは、意味をなさなくなってしまうというのに。
常界の始まりの地、聖巫女ナルルもその場所にいた。そして炎咎甲士が聞いたのは、すべての血の繋がり。創醒の聖者の血を引く堕精王。だから彼は、あの方の子なの。その堕精王からその血を受け継いだ聖神。その血の繋がりがもたらす悲劇に、炎咎甲士は怒りを隠せずにいた。親子って、そういうもんじゃないだろ。
もう、刻の流れは止められない。繰り返し争う統合世界の歴史。ユルルはただ、その事実を悲観していた。だからこそ、聖なる扉は正しく使う必要があったのです。そのために、聖なる扉は生まれたのですから。そして、聖なる扉はひとつとは限らない。そうです、あなたが壊したのは欠片のひとつに過ぎないのですから。
そして、聖巫女ユルルは続けた。それが扉の形をしているのか、それとも人の形をしているのか、そもそも形をなしているのか、そのすべてをあなたは知らないでしょう。もし、すべてを知ってしまったら、あなたは帰ることが出来ないかもしれない。それでも、聖なる扉のすべてを知りたいというのでしょうか。
それがいつ生まれたのか、どう生まれたのか、どこで生まれたのか。そのすべてが明らかにならなくとも、いまそこにそれが存在しているという事実は、そのすべての肯定だった。そして、その絶対の存在の血がもたらした数多の悲劇。その血がなぜ禁忌とされたのか。聖なる扉にまつわる物語は、ひとつに集約される。
これは、もしもの話。ねぇ、知ってるかな。何気ない休日、ヒカリのひとことから始まった小さな遊び。友達同士ね、Tシャツのプレゼントをし合ったら、一生の友達になることが出来るんだって。だからね、これをあげる。友達へのプレゼントには、自分の顔がでかでかと印刷されていた。ちょっと、恥ずかしいかな。
これは、もしもの話。こんなの着られないわ。ユカリはプレゼントをそっとしまった。大丈夫だよ、ほら可愛いでしょ。そう言いながら上着を脱いだ友達が着ていたのは、自分がでかでかと印刷されていたTシャツだった。ほら、だから早く着てみてよ。少し恥ずかしがりながらも、そっとTシャツに袖を通したのだった。
これは、もしもの話。で、これは一体なんなのかな。それはオレが聞きたい。困惑するふたりの王。今朝起きたら届いてたんだ。そして、片方の王、オベロンはさらに頭を悩ませる。いったい、どっちがどっち宛なんだろう。なんだ、ずいぶんお気楽な悩みだな。そして、もう片方の王は微笑ましく見守っていた。
これは、もしもの話。で、どうしてこうなるんだ。微笑んでいた片方の王、ヴラドは目の前の不思議に目を丸くしていた。だって自分で自分を着るのは恥ずかしいじゃないか。そういう問題じゃない。なんでオマエは、ありのままに受け入れてるんだよ。目の前には、自分のTシャツを着た王が。仕方ない、オレも着るか。
これは、もしもの話。あいつら、喜んでくれるかな。ふたりの王へ、嫌がらせに近いプレゼントをした張本人はひとり、満足げな笑顔を浮かべていた。さてと、それじゃあ日々の日課でも始めようか。そして、ヒスイは自らが印刷されたTシャツに袖を通し、いつものメニューをこなし始めた。まずは腕立て伏せ、8万回。
生まれながらに王である男に、幼い日の記憶はなかった。雨に打たれながら、泥にまみれながら、それでも遊び続けた記憶も、友人も存在していなかった。だが、そんな男に出来た友人。だけどもう、友ではいられないんだ。ありがとう、さよなら。
生まれながらに王である男に、幼い日の記憶はなかった。雨に打たれながら、泥にまみれながら、それでも遊び続けた記憶も、友人も存在していなかった。だが、そんな男に出来た友人。だけどもう、友ではいられないんだ。ありがとう、さよなら。
在りし日の魔王の苦渋の決断。それは王故の決断。もし、自分が王という存在でなければ。争いは起きなかっただろう。だが、自分が王という存在でなければ。出会えなかっただろう。あぁ、そうさ、オレたちは初めから、こうなる運命だったんだ。
そのTシャツを着るのは、どんなときだろうか。喧嘩をしてしまった夜だろうか。仲直りをした朝だろうか。そこに存在しているのは、友人を想う気持ち。いつまでも、友達でいたいな。それは少女の、単純でいて、大切な願いだった。
そして、ヴラドが解放した竜の力。オレこそが、天界にとっての恐怖だってこと、教えてやるよ。手を振り払うたびに吹き飛ぶ大地。荒れる天候。そうさ、オレは魔王なんだ。あぁ、天界なんか滅ぼしてやるさ。オマエの家族を、そのすべてをな。
滅び行く天界を前に、オベロンの脳裏をよぎるのはかつての温かな思い出。止めろ、止めてくれ。あぁ、それでいいんだ。満足げな笑みを浮かべたヴラド。そう、オレは魔王で、オマエは妖精王なんだから。そしてオベロンは最後の一撃を放つのだった。
 【追想】美宮殿コロッセオ
【追想】美宮殿コロッセオ *【追想】美宮殿コロッセオ
*【追想】美宮殿コロッセオ 【追想】不夜城ナイトメア
【追想】不夜城ナイトメア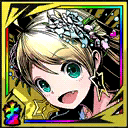 ヴィレヴァンエリア:ヒカリ
ヴィレヴァンエリア:ヒカリ 聖戦:終章Ⅰ
聖戦:終章Ⅰ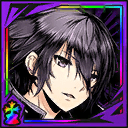 聖戦:終章Ⅰ
聖戦:終章Ⅰ