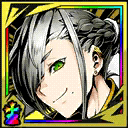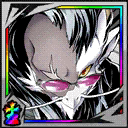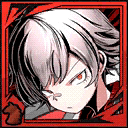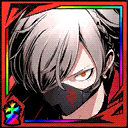STORIES 2017年4月7日のストーリー
この日に実装されたストーリーの一覧です。
-
 扉の先へ:序章・アカネ
扉の先へ:序章・アカネ
♯01 扉の先へ:序章・アカネ金色の光が止んだとき、アカネは自分が生まれ育った家にいた。暖かな縁側、台所から響く包丁の音。そして、アカネが自分の死を直感したのは、目の前に懐かしい男が現れたからだった。久しぶりだ、アカネ。そこにいたのは、炎才パブロフだった。 -
 扉の先へ:序章・アカネ
扉の先へ:序章・アカネ
♯02 扉の先へ:序章・アカネ縁側に並んだ親子。ここはどこなんだ。きっとここが再創された世界、誰しもが幸せになれる世界……から、外れた例外の世界だろう。アーサーが下した世界の決定、それはディバインゲートを使用し、世界を再び構築すること。じゃあ、なんで俺は。 -
 扉の先へ:序章・アカネ
扉の先へ:序章・アカネ
♯03 扉の先へ:序章・アカネなぜ、アカネが例外の世界に存在していたのか。それはきっと、オマエが知ったからだろうな。アカネが常界の始まりの地で知ったディバインゲートの真実。そう、扉そのものでもあるアイツが、オマエをこの世界へ隔離したんだ。次の季節の為へと。 -
 扉の先へ:序章・アカネ
扉の先へ:序章・アカネ
♯04 扉の先へ:序章・アカネ俺はそんなこと、望んじゃいない。俺たちは一歩ずつ、それでも前に進んできた。道を踏み間違えることだってあったよ。だけど、俺たちはイマを生きたいんだ。扉がもたらす未来なんか知らない。俺たちの未来は、俺たちが作っていくもんなんだから。 -
 扉の先へ:序章・アカネ
扉の先へ:序章・アカネ
♯05 扉の先へ:序章・アカネパブロフが突き出した拳。派手に壊してこいよ、そのオマエの拳で。アカネが突き出した拳。あぁ、当たり前だ。茜色に燃える夕日が照らしだしたのは、親子によって交わされた最後の約束。これで、本当にお別れだ。アカネ、オマエはイマを生きろ。 -
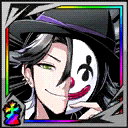 WEGOコラボXII
WEGOコラボXII
GOD LOVES YOU!:神級神は人々を愛している。ボクはボクなりに愛しているつもりなんだけどね。ニヤリと笑う右側の面。そう、愛の形はそれぞれである。そんな想いが込められたグレーのパーカー。どうだい、似合ってるだろ。そんな姿を見て、左側の面は呆れていた。 -
 WEGOコラボXIII
WEGOコラボXIII
GOD ONLY KNOWS!:神級すべては神のみぞ知る。そうさ、私は全部知ってるし、人間は全部知らないの。余裕の笑みを浮かべた左側の面。どうして右側の面が泣いてるのかって。単純で簡単な疑問。そんなの、デザインバランスに決まってるじゃん。神才はいつもの神才だった。