銃に込めるのはそれぞれの想い。打ち抜くのもそれぞれの想い。たった一発、されど一発、その一発に込めた想いがもう一つの想いを打ち抜いた時、残された想いはそのままの想いでいられるのだろうか。それこそが銃へとかけた想いの重さなのである。
ごめんね。さよなら。ありがとう。さよなら。いつか会う日まで。さよなら。別れの度に強くなる想い。人差し指が引き金を引く度に、後戻り出来なくなる想い。かけるのは自己正当という暗示。振り向いてしまった時、その全ては崩れ去ってしまう。
思春期の少年達には夢があった。その夢は人を不幸にする夢だった。だけど、それでも少年達の夢には違いなかった。果たしてそれを夢と呼べるのだろうか。引き金は世界を壊す。壊し続ける。それでも少年達は必死だった。世界の欠片は涙に変わる。
壊れた世界の欠片は涙に変わり、壊した少年達は涙を流すことはなかった。僕達は何も間違っていない。それは片一方の世界の見解。もう一方の世界の見解はどうだろうか。決して少年達を許してはいけない。正しい世界の角度など、存在しないのだ。
戦場では風の流れを読んだ者こそが勝者となる。そんな言葉が残されていた。一人の英雄は言った。それは弾道だと。一人の悪雄は言った。それは戦況だと。戦場に吹き荒れる数多の風、それは兵の心を揺さぶるのに十分な存在でもあったのだった。
狙うのは頭。それは個の話でもあり、輪の話でもあった。戦場では誰もが兵士という単位でしかなく、命の器でしかない。僅かな銃弾で続く痛みを最小限に抑え、そして犠牲を少なくする為に頭を狙う。それは実に効率的であり、人道的なのであった。
誰が一番背が高いか、誰が一番勉強出来るか、誰が一番運動出来るか、そんなこと、彼らにとってはどうでもよかった。ただ、たった一人、三人の輪を乱す発言をした。俺が一番モテる。そんな帰れない日を懐かしんでいると、授業の終了の鐘が鳴った。
敗者が存在すれば、当然勝者が存在する。勝者が存在すれば、当然敗者も存在する。表裏一体の勝ちと負け。多くの勝ちが負けを生み、多くの負けが勝ちを生む。そしていつか気付く時が来るだろう。勝者は敗者のおかげで、勝者でいられることに。
命あるもの、いつか死を迎える。生の終着点が死であることに違いない。だったら、さっさとゴールさせてあげましょう。それが射撃練習で教えられたことだった。じゃあ何故、先生はゴールしないんですか。物事には、過程が大切なこともあるんです。
終わりが始まりだとしたら、死は生なのだろうか。確かに始まりなのかもしれない。では、全員が始まりを求めるのか。それは決して違う。それならば、死とは誰もが望むことではない、という結論が導き出される。また一つ、矛盾は解消された。
長い戦いの中、勝負は時に一瞬で決まる。いや、そうではない。勝負が決まる時はいつも一瞬なのだ。勝者の証も、敗者の烙印も、その二択を決するのはいつも一瞬なのだ。その過程に、優勢劣勢があったとしても、最後の結果こそが全てなのだった。
時間は残酷である。かけた時間が長ければ長いほど、その時間を失った時の敗北感は強くなる。だが、時間は平等ではない。だから、可能な限り、一撃で仕留める。少ない時間、少ない弾数で終わらせるのは、相手の為であり、自分の為でもあった。
 魔教室フレイムクラス
魔教室フレイムクラス 魔教室フレイムクラス
魔教室フレイムクラス 魔教室アクアクラス
魔教室アクアクラス 魔教室アクアクラス
魔教室アクアクラス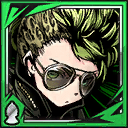 魔教室ウィンドクラス
魔教室ウィンドクラス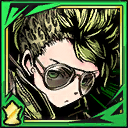 魔教室ウィンドクラス
魔教室ウィンドクラス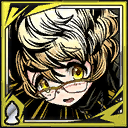 魔教室ライトクラス
魔教室ライトクラス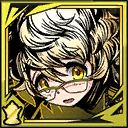 魔教室ライトクラス
魔教室ライトクラス 魔教室ダーククラス
魔教室ダーククラス 魔教室ダーククラス
魔教室ダーククラス 魔教室ノーンクラス
魔教室ノーンクラス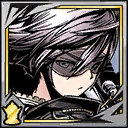 魔教室ノーンクラス
魔教室ノーンクラス