美宮殿に呼び出された炎の美女。あなたには、きっと彼女の相手をしてもらう。それは魔界の黒い森の赤い女王。私、彼女を知っているわ。そして続く言葉。へぇー、俺もそいつ、良く知ってるぜ。なぜか炎の美女の隣、そこには炎刑者がいたのだった。
花はいつか、散ってしまうものなの。水も滴る絶世の美女は思い出を眺めていた。どうせ散るなら、綺麗にね。その言葉から感じとった不穏な覚悟。これは私からの命令です。絶対に、もう、誰も死んだら駄目です。それじゃあ、何の意味もないから。
風の美女はひとりだった。あの頃は、いつも四人だったのに。同じ世界で生まれたにも関わらず、離れ離れになってしまった彼女の耳に聖戦の話は遠かった。だったら目を覚まさせるのが、あなたの役目じゃないかな。湖妖精はそう優しく声をかけた。
仕事終わりの光妖精王と共に浴槽に浸かる光の美女。あら、また大きくなったんじゃないですか。うーん、どうだろう。だが、そこには大きな膨らみが浮かんでいた。柔らかな弾力、弾かれる水、そう、そこに浮かんでいたのは光の猫のお腹だった。
失恋により家出をした友人は未だ行方不明だった。奴はもう死んでるようなものだからな。そんなことを言いつつも闇の美女は心配だった。最後に友人を目撃した人の話では、隣に仮面の男がいたと言う。間違った事にならなければ良いが。心配は続く。
明日の天気は晴れ、明後日も晴れ、明々後日も晴れ、そんなことを夢見てた。だが、現実は違っていた。明日は曇り、明後日も曇り、明々後日も曇り、それは晴術師の心模様。もやもやから、逃げるわけにはいかないんだね。そして彼女は覚悟を決めた。
人間が全てを惑わす。私達は、私達の世界で生まれ、生き、そして死ぬべきなの。そう、人間は全ての元凶なのよ。その想いを捻じれていると言った者もいた。だが、それは自然なことであると言った者もいた。これは裏切りなんかじゃありませんから。
こんな時に悲しいバラードなんか聴きたくないぜ。風術師が耳元の風を、悲しいと感じるのは珍しいことだった。いやこれはアンセムか、忘れるとこだったぜ、ベイベ。思い出したのはそう、伝説的なミュージシャンはみな、若き最期を迎えていた事実。
眩術師は、湖妖精の考えが信じられなかった。奴の力に頼るということは、一歩間違えれば天界は跡形もなく消えるということだぞ。それでもね、そうする以外に方法はないの。何をそんなに焦っている。そう、珍しく湖妖精に焦りがみえたのだった。
魔物はみな、死ねばいいのよ。何が彼女をそこまで掻き立てるのか。裏切り者の闇精王も、あっちにいるのよね。闇の力が、魔物のものだなんて、誰が決めたのかしら。魔物がいなくなれば、私の両親は。それにもう、隠れて生きる必要もなくなるのよ。
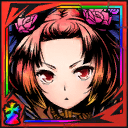 美女のお清めⅠ
美女のお清めⅠ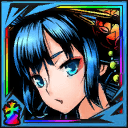 美女のお清めⅡ
美女のお清めⅡ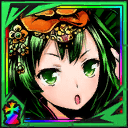 美女のお清めⅢ
美女のお清めⅢ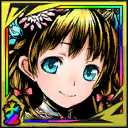 美女のお清めⅣ
美女のお清めⅣ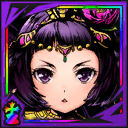 美女のお清めⅤ
美女のお清めⅤ 明日の天気Ⅰ
明日の天気Ⅰ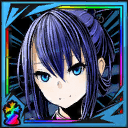 明日の天気Ⅱ
明日の天気Ⅱ 明日の天気Ⅲ
明日の天気Ⅲ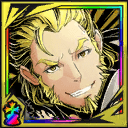 明日の天気Ⅳ
明日の天気Ⅳ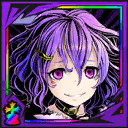 明日の天気Ⅴ
明日の天気Ⅴ