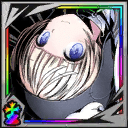神界から統合世界を見つめる男がいた。視線の先にはその身を隠していた湖畔を後にしようとする咎人が。もう一度だけ、相手をしてやろう。落ち着きながらも、その瞳には炎が灯っていた。炎と炎が再会を果たす時、そこには一体何が残るのだろうか。
あの時よりもイイ男になったじゃない。艶やかな視線の先には千本鳥居を通り抜けた咎人が。何度だって奪ってあげる。口元は緩んでいた。アタシは罪に濡れた男が好きなのよ。そう言いながら視線を移した先、そこにはもう一人の罪に濡れた男がいた。
何故あの時、あの少女を手にかけたか、その答えをもらってなかったね。悪戯な神は問いただす。あの少女って、誰。寝ぼけ眼のまま返す風の神。あの少女を、助けにきた。そう言いながら指差した竜界、だが指差したはずの少女は既に姿を消していた。
光の神は羨ましそうに天界を眺めていた。やっぱり、若いってイイねぇ。必死に走り回る光妖精王は汗を流しながらも笑顔を振りまいていた。でも、若さって残酷よ。それは幾度となく繰り返される争いを見てきた彼女だからこそ、こぼした言葉だった。
あー、マジでイラつくわ。闇の神は二人の少女を思い出していた。今、あの椅子には片っぽが座ってるね。遠くから眺めていたのは魔界に位置する終わらない夜の城。でもいいわ、希望を失った王は、神に縋るしかなくなるのよ。だから、希望を奪えば。
縛り付けて監視するだなんて、本当に趣味が悪いんだから。無の神が眺めていたのは常界だった。英雄という言葉に、何の意味があるのかな。その答えは簡単だった。そっか、みんな肩書きを求めては、肩書きに溺れてしまう、哀れな生き物だったんだ。
いつの時代も、手のかかる人達だ。だが、悪戯な神様は喜びの笑みを浮かべていた。でも今はまだ、その時じゃないから。鼻へとかざす人差し指。聞こえるかい、かすかな希望が。見つめる手のひら。大いなる絶望の為には、大いなる希望が必要なのさ。
民は王に縋るとしたら、王は何に縋るんだろうね。悪戯神ロキは問いかける。神に縋るしかないよね。それは下らない自問自答。もっと無様に争えばいいよ。遥か彼方の神界<ラグナティア>から、美味しそうに見つめる統合世界<ユナイティリア>。どうせ聖なる出口<ディバインゲート>なんて存在しないんだから。
勝手についてきちゃ駄目だよ。そう言いながらも優しく頭を撫でる悪戯な神。だが、言葉を発することのないタマの視線は常に一人の男へと向けられていた。君たちは、似たもの同士なのかもしれない。言葉を発しないもう一人の男。彼のことが気になるのかな。なぜ少女が彼を気にかけるのか、全ては思い出の中だった。
狂騒獣タマは、彼らのやりとりをじっと見ていた。悪戯神のすぐ隣で綴り続ける少女、その隣で虚ろな目で空を見つめる堕王、そんな三人を気にせず研究に没頭する堕闇卿。更に四人を気にも止めないのは客人であるはずの神才。まだ、彼らは来ないみたいだね。悪戯神達は待っていたのだった。退屈は好きじゃないんだ。
タマは果たして猫なのでしょうか。どう見ても人の姿をしている。だが、実際にコタツで丸くなっている。ならば、やはり猫なのでしょう。だが、猫じゃらしには興味がなかった。やはり猫ではないでしょう。そんな結論を導き出したのは堕闇卿だった。
私は、神に選ばれたのですね。堕闇卿ヘンペルの創り物の心は囚われていた。美しい神よ、美しい心よ、あぁ、今日も世界は美しい。同士も、そうは思わないかね。問いかけた先、堕王は虚ろな目で世界を眺めるのではなく、ただ映していた。そうか、同士も美しく感じるか、それは良かった。独り言は、響き続いた。
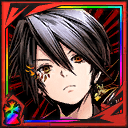 黄昏の行方Ⅰ
黄昏の行方Ⅰ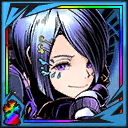 黄昏の行方Ⅱ
黄昏の行方Ⅱ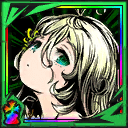 黄昏の行方Ⅲ
黄昏の行方Ⅲ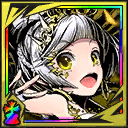 黄昏の行方Ⅳ
黄昏の行方Ⅳ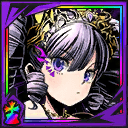 黄昏の行方Ⅴ
黄昏の行方Ⅴ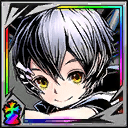 黄昏の行方Ⅵ
黄昏の行方Ⅵ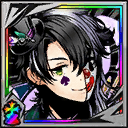 黄昏の行方Ⅶ
黄昏の行方Ⅶ とある休日Ⅵ
とある休日Ⅵ