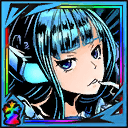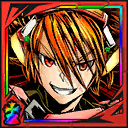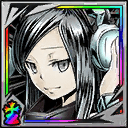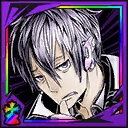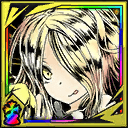水とは何か。その答えを渇望した少女は、幾つもの実験の果て、水のみを動力とする機体を創り出した。ケルビンと名付けられたその機体は、世界の気候を狂わせる程の性能を持ちながらも、戦争の表舞台に現れることは無かった。全ての水が、やがて海へと還る様に、この機体もまた、深い海の底へと沈んでいった。
あらゆる生命に満ち溢れた海の一角が、一夜にして死の氷海と化した。その現象を、人々は聖なる扉の出現に伴う異常気象と結論付けていた。全ての生物が活動を停止した静かな海の中で、水冷機ケルビンだけが優雅に泳いでいる。何故、再び彼女が目覚めたのか。それは、創造主のただの気まぐれだろうか。それとも。
水は空から降り、地を流れ、海へと還り、また空へ昇る。生命もまた、生と死を巡るもの。この近似性から立てられた仮説。検証の為に創られた機体は海の底で活動を停止した。それは失敗だったのか、知っていたのは神と呼ばれた天才ただ一人だった。
熱とは何か。少女の頭に浮かんだ一つの疑問は、やがてジュールと呼ばれる答えを創り出した。その機体内で熱が生まれ、その熱が機体を動かし、また新たな熱を生む。だけど、辿り着いた答えは、また幾つもの疑問を少女の中に炙り出す。結局、その機体に火が灯ることが無いまま、一つの争いが終わりを迎えていた。
また争いが始まるんだね。それは少女にとって諦めであり、喜びでもあった。人間が生み出した炎が、まさか神の領域にまで届くとは。あの頃とは、また違った答えが見つかるかもしれないね。炎熱機ジュールに初めて灯された炎は、機体の融点を遥かに超えた温度で燃え上がる。今回は最後まで、見届けることにするよ。
全ての生命は産まれた時に熱を持ち、死に絶える時に熱を失う。命は燃え、舞う火の粉がまた新たな命となり、世界を燃やす。熱は活力の象徴。かつて、永遠の命を模して作られた機体が、その熱量に耐えきれる器を持たされなかったのは何故だろうか。
音とは何か。音とは空気の振動であり、生ある者が動く時、必ず音が発生する。そこから定義されたのは、無音は死であるということ。その検証の為に創り出された機体がデシベルだったが、始められた検証には一つ誤算があったことに少女は気付いた。その後、機体は物音一つしない無音空間で、長い長い眠りについた。
神と竜が争っていた頃、世界に溢れていた悲しい音。だけど微かな音さえ、ここには届かなかった。この無音空間で眠っていた無音機デシベルを目覚めさせたのは、届かない筈の悲しい音。再び戦争が始まろうとしていた。さてと、実験の続きでもはじめよっかな。少女の隣、原初の機械もまた、不敵な笑みを浮かべた。
世界には幸せな音、悲しみの音、その全てが混ざり合い存在する。それは世界が生きている証明なのかも知れない。もし世界から音が消えたら、世界は死ぬのだろうか。それを検証する手段が考案されたが、一つの大きな懸念により、実験は見送られた。
風とは何か。時に風は冷たく、微かな命の灯火を吹き消してしまう。時に風は暖かく、木々が産んだ新たな生命を運んでいく。そんな風に興味を持った少女によって創り出されたガル。兵器でありながら、その機体は戦場ではなく、高い雲の上へ姿を消した。風に吹かれた生と死が、ゆらり揺れる世界を見下ろしながら。
この世界を流れる様々な風。竜の吐息、悪魔の羽ばたき。各々の想いを抱えて疾駆する者達。数多の風が空へと舞い、その機体にこびり付いた錆を一つ残らず払い落としていく。風速機ガルの体内に再び風が宿る時、世界の風向きが変わり始めた。いや、風向きが変わり始めたからこそ、再び風が宿ったのかもしれない。
風は運んだ。小さな摩擦から生じた、小さな火花を。風は焚きつけた。その種火が、やがて炎になるまで。風は記憶した。かつて神と竜の間で起きた、大きな争いの傷跡を。そして、変わり始めた風向き。この世界もまた、大きく変わろうとしていた。
磁とは何か。それは異なるものが引き合い、同種のものが退け合う力。生と死は異なる事象であり、きっと引かれ合う。さて、その二つが一つになる位まで近付いた時、その中心には一体何があるのだろうか。少女は確証を得る為に一体の機械を創り出した。長く続いた戦争の中心で、テスラはずっと記録し続けていた。
出会う筈の無かった異なる世界に住まう異なる種族。偶然の出会いに引かれ合い、やがて近付き過ぎた両者は反発し合う。小さな反発はやがて大きな反発へ。そして今もまた、世界のバランスは崩れ、生と死が引かれ合う戦争が始まろうとしていた。闇磁機テスラもまた、再び動き出す。少女が求める答えを記録する為に。
生と死は近づいたり離れたり、何度も繰り返されてきた。そこに意味は有るのだろうか。未だ答えは見付からない。もし意味が有るのなら、多くの犠牲にも大義があったと言えるだろうか。その答えが見付かるまで、観察は続けられる。そう、何度でも。
光とは何か。降り注ぐ光に、目を細めながら少女は問う。何者にも等しくその恵みを分け与える光を、もし自由に操ることが出来たなら。光を動力とする機体が創り出された頃、長引く戦争に空は閉ざされ、その機体が動くことは叶わなかった。今は、おやすみなさい。少女の優しい言葉に、ルクスはその目を閉じた。
降り注ぐ光の中、すやすやと眠り続ける光明機ルクス。長く続いた神と竜の争いは終わり、再び空には光が満ちていた。やがてその目覚めは、新たな戦争の始まりと共に。ママはどこ。目を擦りながら彼女は呟く。目覚めたばかりの兵器は、母を求めて初めて外の世界へと向かう。自らに課せられた役目も知らぬままに。
始まりは闇だった。この世界に光は無く、闇が世界の全てだった。それは一説。始まりは光だった。この世界に闇は無く、光が世界の全てだった。それも一説。だが、互いに、それを光だと、闇だと認識出来たのは何故だろうか。始まりは無だったのに。
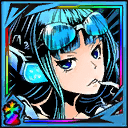 失工場ケルビン
失工場ケルビン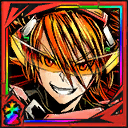 失工場ジュール
失工場ジュール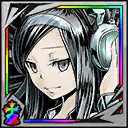 失工場デシベル
失工場デシベル 失工場ガル
失工場ガル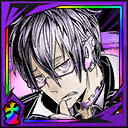 失工場テスラ
失工場テスラ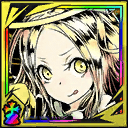 失工場ルクス
失工場ルクス