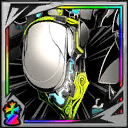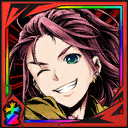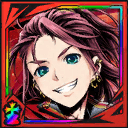王都を取り囲むように姿を現したおびただしい数の【量産型ヨトゥン】。みな、同じ姿形をしていたのは、量産型であるが故の当然の事実だった。なぜ、神の手を持つほどの神才が、わざわざ量産型を開発したのか。それは神が人間に対して覚えた好奇心と、そして好奇心による探求の果ての一つの解答でしかなかった。
殲滅行動を開始した量産型。だが、偽物の機体は臆することなく次々と撃墜を繰り返す。再起動<リブート>、モード:――。立ち昇る白煙、雨に濡れた残骸。そして、偽物の機体一機が全ての量産型を撃墜し終えた時には姿を消していた神才と原初の機体。だからこそ、神才達は知らない。偽物の機体の七番目の姿を。
雲行き怪しくねぇか。馴れ馴れしく話しかけた男は窓越しの雨空を見つめていた。口の利き方は教えたはずだが。馴れ馴れしく話しかけられた男は苦言を呈していた。いいのか、放っといて。馴れ馴れしく続けた男。手なら打ってある。馴れ馴れしく続けられた男。炎聖人の執務机上、そこには腰をかけたフォルテがいた。
なんだ、俺にお願いごとじゃなかったのか。ふてくされたまま話し続ける男。貴様に課す仕事など、一つしかない。その言葉で動いた眉。なぁ、歌の仕事か。違う。一言の否定。貴様の歌に興味などはない。だが、貴様の腕に興味はある。表の顔は常界を揺るがすポップスター、そして裏の顔こそが炎奏徒フォルテだった。
自分を生んだ母が存在するのなら、その母にもまた、自分を生んだ母が存在する。そして、その母にもまた、母は存在する。無限に遡った果てに辿りついた女。どちらが生き残るか、見せてもらおうか。さぁ、争うがいい、我が息子達よ。始祖リリンは、その手にした鳥かごに閉じ込められた聖戦の行方を見守っていた。
うーん、やっぱりこっちの方が人間らしいね。神才は無数に並んだ巨兵を前に、一人で結論へと達していた。うんうん、やっぱりこの無個性が人間らしいよ。神才の瞳には、人間と量産型の巨兵が同じように映っていたのだった。つまり、これで完成だ。
帰って来い。聖神となったかつての聖王、アーサーへと向けた一斉攻撃。込められたそれぞれの想い。巻き起こる粉塵、鳴り響く衝撃、零れ落ちる涙、噛み締める唇、色褪せた永遠の思い出。だが、それぞれの想いは、六つの影により遮られたのだった。
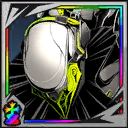 神兵場ヨトゥンヘイム
神兵場ヨトゥンヘイム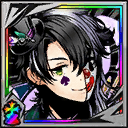 大いなる希望:終章Ⅴ
大いなる希望:終章Ⅴ