STORIES 2013年9月30日のストーリー
この日に実装されたストーリーの一覧です。
-
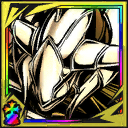 極光塔オーロラ
極光塔オーロラ
天昇る機竜警戒レベル3の警報が聞こえた時、もはや聞き慣れてしまったプロテクトの解除音が聞こえた。そう、再び現れたのは光の大型自立型ドライバ、第五世代の天昇る機竜。予期せぬ敵の出現に、宝石塔の警戒態勢が予測出来ないものへと変わった。 -
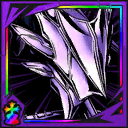 極光塔オーロラ
極光塔オーロラ
空翔る機竜警戒レベル4、真っ先に聞こえてきたのはプロテクトの解除音。光の天昇る機竜に続き、現れたのは闇の空翔る機竜。闇の力を蓄えたその機械の身体は、自らの意志で予期せぬ侵入者へと、終わりを、永遠に続く闇を与えようとしていた。 -
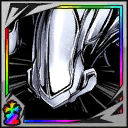 極光塔オーロラ
極光塔オーロラ
地走る機竜警戒レベル5、9回目のプロテクトの解除音。地走る機竜の出現はもはや予測の範疇となっていた。7つ連なっていた宝石塔の最期、目にも止まらぬ速さで繰り広げられる攻防、加速したその先に、天界<セレスティア>への道が待っている。 -
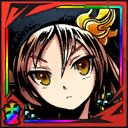 赤帝楼閣スザク
赤帝楼閣スザク
始まりの炎開かれた扉により、訪れようとしていたのは黄昏の審判。噂ばかりが先行しているその真実を目指し、その足を赤帝楼閣スザクへと。待ち構えていたのは始まりの炎を司る大精霊。真実へ近づかせるか計る為の、精霊による力試しが始まる。 -
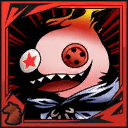 赤帝楼閣スザク
赤帝楼閣スザク
妖精の火遊び精霊に認められた者だけが進むことの許された楼閣で、次に待っていたのはきまぐれな炎の妖精。口ずさむ歌、放たれる炎、妖精の火遊びが行く手を遮る。だけどそんな火の妖精には、水を浴びせて一網打尽にしてしまえばいいだけのことだった。 -
 赤帝楼閣スザク
赤帝楼閣スザク
狐の嫁入り赤帝楼閣に伝わる伝承、狐の嫁入りになぞらえた3匹の炎狐。炎の精霊により、以前よりも力を増した炎の狐が燃やす炎。燃え盛るのは赤く染められた楼閣。炎を越えたその先に、炎が浮かび上がらせた道へと辿り着くことが出来る。 -
 赤帝楼閣スザク
赤帝楼閣スザク
乙女の恋談議恋に恋焦がれた乙女の恋談議。世界の情勢に興味がないわけじゃないけれど、それよりもやっぱり身近な恋にばかり興味があるのはお年頃の炎の妖精。火傷する程の燃える恋を、冷たく冷えた水で冷ましてあげない限り、ここから先へは進めない。 -
 赤帝楼閣スザク
赤帝楼閣スザク
破壊力の暴走非常警報を告げる鐘が鳴り響いた。鈍く、重い、その鐘の音が告げたのは破壊力の暴走。リミッターの解除された第五世代の大型ドライバによる破壊力の暴走。今、赤帝楼閣は、上位なる存在の悪戯により、脆くも崩れ去ろうとしていた。 -
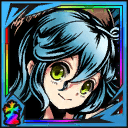 青帝楼閣セイリュウ
青帝楼閣セイリュウ
始まりの水辿り着いた青帝楼閣セイリュウ、最初にお出迎えをしてくれたのは水を司る大精霊。そんな始まりの水の起源<オリジン>が優しく語りかけるのは黄昏の審判の始まりの始まり。母なる海の様な優しさは、時として厳しさへと変わった。 -
 青帝楼閣セイリュウ
青帝楼閣セイリュウ
ただの水遊び降り出した雨、楼閣の縁側でしばしの雨宿り。そんな雨の中、嬉しそうに歌って踊るのは水の妖精。出来たばかりの水溜まりで飛び跳ね廻る。降り続き、勢いを増した雨は、ただの水遊びだった妖精の悪戯を、悪意のない悪意へと変えた。 -
 青帝楼閣セイリュウ
青帝楼閣セイリュウ
水弾く毛並み降り止むことのない強い雨、雨漏りすら出来てしまった青帝楼閣。滴る雫を浴びながら、その水弾く毛並みは氷の狼。むしろ浴びれないことに残念な表情を浮かべた狼達は、そのうっぷんを晴らすよう、晴れない空へと遠吠えを上げる。 -
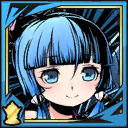 青帝楼閣セイリュウ
青帝楼閣セイリュウ
乙女の嗜みしばらく楼閣を進んだ先で、お出迎えをしてくれたのは水の妖精、清らかな乙女。疲れた者を癒す為に尽くすことこそが、乙女の嗜み。そして、それはこの統合世界<ユナイティリア>に生きる全ての男性の、憧れの的となっていた。 -
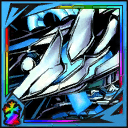 青帝楼閣セイリュウ
青帝楼閣セイリュウ
潜水力の暴走響き渡る鐘の音は、降りしきる雨音でさえも消すことは出来なかった。聞きたくなかった非常警報。止まない雨の中、リミッターの解除された第五世代自立型ドライバの潜水力の暴走。雨の中を泳ぐ機竜に、青帝楼閣は押し流されかけていた。 -
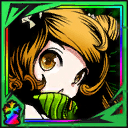 緑帝楼閣ゲンブ
緑帝楼閣ゲンブ
始まりの風緑帝楼閣に吹いた風、それは始まりの風。天界<セレスティア>からお目見えした風を司る大精霊は向かい風を吹かせた。そして、この強い向かい風を見事止ませることが出来た時は、更に強い追い風を吹かせると、そう約束をして。 -
 緑帝楼閣ゲンブ
緑帝楼閣ゲンブ
楼閣の居候風に乗ってゆらゆらと、住み着いてしまったのは悪戯な風の妖精。楼閣の居候は何をするでもなく、ただ風の行方をぼんやりと眺めていた。開かれた扉により変わってしまった風が、また、更に変わり始めたことに、気がついていたのかも知れない。 -
 緑帝楼閣ゲンブ
緑帝楼閣ゲンブ
猪突神進風を司る大精霊が作り出した追い風に乗ったのは、開かれた扉<ディバインゲート>を目指した者達だけではなかった。そう、風に乗り、猪突神進の如く追いかけてくる風の猪達。追いつかれるよりも前に、楼閣を抜けることが出来るか。 -
 緑帝楼閣ゲンブ
緑帝楼閣ゲンブ
乙女の昼下がり吹きつける風が少し冷たく、だけど心地よい昼下がり。緑帝楼閣の一角、緑色のコートに袖を通した乙女の昼下がりは優しい緑の香りがした。摘んだばかりの四つ葉に、審判の訪れを、阻止できるようにと、ただそれだけを願っていた。 -
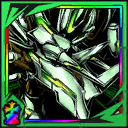 緑帝楼閣ゲンブ
緑帝楼閣ゲンブ
進撃力の暴走遠くから音が聞こえた。そしてその音は、徐々に大きく、大きすぎる程に。非常事態に気が付き、警報の鐘が鳴らされた頃にはもう、その鐘の音は轟音にかき消されていた。進撃力の暴走は、避難する時間さえも与えてはくれなかった。 -
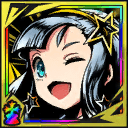 黄帝楼閣コウリュウ
黄帝楼閣コウリュウ
始まりの光黄帝楼閣に差し込んだのは始まりの光。天界<セレスティア>からお目見えした光を司る大精霊が発した光は輝かしく楼閣を包みこんだ。優しい光の、その優しさに甘えることなく、自らの足で歩きだせた時、開かれた扉の真実へ近づくことが出来る。 -
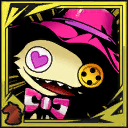 黄帝楼閣コウリュウ
黄帝楼閣コウリュウ
鮮やかな楼閣光に導かれ、やってきたのは悪戯な光の妖精。光に包まれた鮮やかな楼閣に、またひとつ、小さな光が集った。その眩さに、目を眩ませることなく、しっかりと前を見る大切さ、それもまた、光を司る大精霊が与えようとした優しさだった。 -
 黄帝楼閣コウリュウ
黄帝楼閣コウリュウ
3つ首の3匹光に集ったのは妖精だけではなかった。3つ首の3匹、そう、魔界<ヘリスティア>の番犬もまた、眩い光に導かれて、この黄帝楼閣へやってきたのだった。首輪の外された番犬は眩い光に惑わされて、忘れられた自制心、鋭い牙を剥いた。 -
 黄帝楼閣コウリュウ
黄帝楼閣コウリュウ
乙女の戦い溢れた光に気が付き、光を憎む者すらも訪れる黄帝楼閣で、光の妖精、戦乙女は自らの、乙女の戦いを繰り広げていた。全ては我が主の為に、その身を呈して放つ光は、楼閣を輝かせ、そして更なる光となり、楼閣全てを包み込んだ。 -
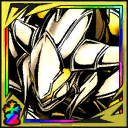 黄帝楼閣コウリュウ
黄帝楼閣コウリュウ
機動力の暴走光に包まれた楼閣が更なる光に包まれる。そして、直後に鳴り響く轟音。それはリミッターの解除された第五世代の自立型ドライバが落とした雷鳴。バーストモードの発動、機動力の暴走が呼び寄せた光は、誰も望まない、悪意ある光となった。 -
 紫帝楼閣ビャッコ
紫帝楼閣ビャッコ
始まりの闇紫色の夜が訪れた時、紫帝楼閣への入り口が開かれた。少し弱気に見える幼い姿、だけどその目には力を宿し、未来を見据えた始まりの闇を司る大精霊は、審判の先にある、約束された未来を、辿りついてはいけない未来を、知らせようとしていた。 -
 紫帝楼閣ビャッコ
紫帝楼閣ビャッコ
楼閣で悪戯楼閣の隅っこで、闇に紛れて悪戯をしていたのは闇の妖精。誰にも気付かれないように、ただひとり遊びをしていたいだけだった。だけど、闇を司る大精霊の訪れに共鳴してしまった闇の力は、隠しておくことが出来ないくらい大きなものになっていた。 -
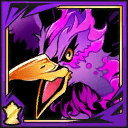 紫帝楼閣ビャッコ
紫帝楼閣ビャッコ
羽音を頼りに訪れた紫色の夜、活動を始めた闇の鴉達は羽音を頼りに集い始める。ここは何かが違う、野生の勘は闇を司る大精霊の訪れを察知した。大きくなる闇の力、闇と闇の共鳴<リンク>はご褒美となり、そして、行く手を遮る大きな脅威にもなった。 -
 紫帝楼閣ビャッコ
紫帝楼閣ビャッコ
乙女の誘惑闇に包まれた楼閣は、闇の妖精、魅惑な乙女にとって最高の楽園だった。繰り広げられるのは誘惑。魅了された者はこの世界に二度と戻ってくることが出来ないほどの乙女の誘惑は、時として、闇だとわかっていながらも、幸せを感じさせるものだった。 -
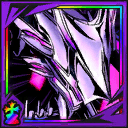 紫帝楼閣ビャッコ
紫帝楼閣ビャッコ
飛翔力の暴走何故誰も気が付かなかったのか。飛翔力の暴走は、闇に紛れ、鐘を鳴らす暇さえ与えず、紫帝楼閣のすぐ側まで来ていた。解除されたリミッターにより増した飛翔力は、全て、予想を遥かに上回っていた。夜の帳の中で、闇に紛れた闘いが始まる。 -
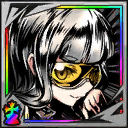 無帝楼閣キリン
無帝楼閣キリン
始まりの無全ての始まりは、何もない。そう、無から全てが始まる。そんな始まりの無を司る大精霊が伝えようとするのはこの世界の理。自らの産まれた理由も、その存在理由すらも知らない大精霊が、無の起源<オリジン>がいう、この世の理とは。 -
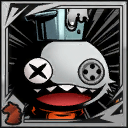 無帝楼閣キリン
無帝楼閣キリン
楼閣の探検何も無い楼閣に、理由も無く現れる無の妖精。自らの意志とは関係のない場所で、産まれてしまった存在理由。自分の存在を隠してしまいたい、誰にも見つからずに、ただひとりで遊びたい、そんな悪戯好きの妖精に、悪意はなかった。 -
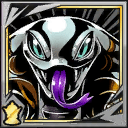 無帝楼閣キリン
無帝楼閣キリン
剥かれた毒牙無の力が集まり始めた無帝楼閣に、にじりより、剥かれた毒牙は魔界<ヘリスティア>の無の蛇のもの。これから何かが、大きな何かが起きようとしている、その前触れを気付かせた野生の勘、防衛本能は毒を更なる猛毒へと進化させた。 -
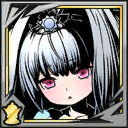 無帝楼閣キリン
無帝楼閣キリン
乙女の微笑何が起きようと、無の妖精、幽霊の乙女にはそんなこと、どうでもよかった。ただちょっとお祭り気分、そんな慌ただしい世界を眺めているのは嫌いじゃなかった。薄らと浮かべた乙女の微笑、それは少しだけでも世界に興味を持てた表れ。 -
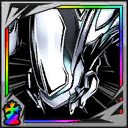 無帝楼閣キリン
無帝楼閣キリン
躍動力の暴走予定調和な大型ドライバの訪れ。そして当然、何者かに外されていたリミッターに、発動されたバーストモード。激化する統合世界<ユナイティリア>に訪れようとしている黄昏の審判を前に、無の力が集った無帝楼閣は窮地に陥っていた。 -
 白帝楼閣シュラ
白帝楼閣シュラ
楼閣の狗鴉蛇最後の楼閣は白帝楼閣シュラだった。炎、水、風、光、闇、無、その全てを司るその楼閣に住まう無数の獣達。魔界<ヘリスティア>の光の犬、闇の鴉、無の蛇は種族を越えて集い、そして審判の日へと向かう統合世界<ユナイティリア>を盛り上げる。 -
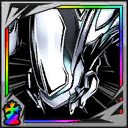 白帝楼閣シュラ
白帝楼閣シュラ
止まらない暴走発動されてしまったバーストモード、永遠に繰り返される止まらない暴走、大型ドライバは約束された未来へと、その足を止めることはない。解除されてしまったリミッターにより、止まらないその動きを止めるには、無理矢理にでも破壊するしかない。 -
 白帝楼閣シュラ
白帝楼閣シュラ
幾つもの牙炎の狐、氷の狼、風の猪、その全てが牙を剥く。幾つもの牙が織りなす獣達の宴。野生の血を身体中に巡らせ、研ぎ澄まされた狩猟本能が踊り出す。それがいったい何の為なのか、獣達に問いかけても、答えなど返ってくるはずもなかった。 -
 白帝楼閣シュラ
白帝楼閣シュラ
制止する者達次第に明るみになるのは「黄昏の審判」の真実。混乱が増し始めた統合世界<ユナイティリア>を制止する者達の訪れ。冷静さを欠如したこの世界ではもう、敵も味方も関係なく、ただ、各々が信じる道を、ただひたすらに進むしかなくなっていた。 -
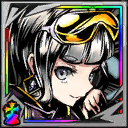 白帝楼閣シュラ
白帝楼閣シュラ
終わりの始まり再び姿を見せた無の大精霊は、自らが生まれた意味に何もなかったことを告げた。そして、何もないからこそ、新しい道へと歩き出せると。何も持たないことは、恥じることではない、何も無いからこそ、約束されることのない未来を、掴みとれると。 -
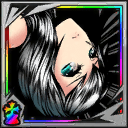 無限ラビリンス
無限ラビリンス
無限への誘い:初級この扉の果てに何が待っているのか、その答えを知る者は、この世界にはひとりもいなかった。そう、その答えは知る者は、この世界よりも遥か上位なる世界に存在し、そして、幾億万と繰り返されてきた歴史と共に、扉の最果てで待っている。