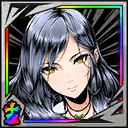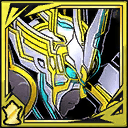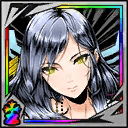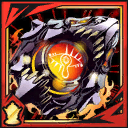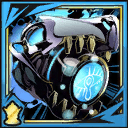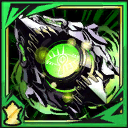STORIES 9月28日
この日に実装されたストーリーです。
-
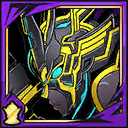 聖なる扉
聖なる扉
聖なる入口:神級聖暦の王により閉じられた扉は悪戯王により再び開かれた。だが、道化竜の償いによる二度目の裏切り、想定よりも早い解放、現れたのは不完全な扉の君だった。神へ抗う塔の最上階、開かれた扉により始まった黄昏の審判は終焉を迎えようとしていた。 -
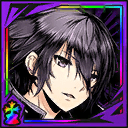 聖戦:ふたりの王Ⅱ
聖戦:ふたりの王Ⅱ
♯06 聖戦:ふたりの王大分鈍ったんじゃねぇのか。オベロンの放つ闇をいとも簡単に弾いてみせるヴラド。そして弾かれた闇が壊す美宮殿の煌びやかな装飾。それじゃ、こっちからいかせてもらうぜ。現れた棺から生まれる無数の光の竜。さぁ、すべてを喰らい尽くしちまえ。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅱ
聖戦:ふたりの王Ⅱ
♯07 聖戦:ふたりの王ひとりの王が攻撃が繰り出すたびに、美宮殿は悲鳴をあげる。激しい音と共に築かれる瓦礫の山。オレ達の舞台にしちゃ、ちょっともろすぎるんじゃねぇか。すでに失われた宮殿の姿。そして、そんな宮殿の上空でふたりの王は変わらず対峙していた。 -
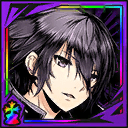 聖戦:ふたりの王Ⅲ
聖戦:ふたりの王Ⅲ
♯08 聖戦:ふたりの王天界の軍勢も、魔界の軍勢も、ただ上空でぶつかり合うふたりの王を見つめていた。いや、見つめることしか出来なかった。少しでも目を離せば、ふたりの姿を見失ってしまう。そう、ふたりの王の戦いは、目で追うだけで精一杯だったのだから。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅲ
聖戦:ふたりの王Ⅲ
♯09 聖戦:ふたりの王かつて、光と闇がぶつかり合ったように、再びぶつかり合う闇と光。どうにか、持ってくれよ。ヴラドが気にかけたのは、仮初の時間。だが、その願いは散る。オベロンの放つ衝撃。それを受け止め切れず、ヴラドの体は地へと打ちつけられたのだった。 -
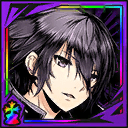 聖戦:ふたりの王Ⅳ
聖戦:ふたりの王Ⅳ
♯10 聖戦:ふたりの王くそっ、こんなときに。それでもすぐに立ち上がるヴラド。そんなヴラドの瞳に飛び込んできたのは、ただ上空のオベロンを見つめる、天界、魔界の両軍勢だった。そして、ヴラドはその眼差しがなにを意味していたのか、すぐに理解したのだった。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅳ
聖戦:ふたりの王Ⅳ
♯11 聖戦:ふたりの王ヴラドを地へと堕とすほどの圧倒的な力。そう、オベロンへ向けられたのは賞賛ではなく、ただの恐怖だった。そして、天界、魔界の両軍勢は同じときに、同じことを想う。互いに協力し、滅ぼすべき相手は、禁忌の血を引くオベロンではないのか、と。