STORIES 2016年9月28日のストーリー
この日に実装されたストーリーの一覧です。
-
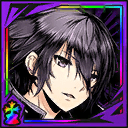 聖戦:ふたりの王Ⅱ
聖戦:ふたりの王Ⅱ
♯06 聖戦:ふたりの王大分鈍ったんじゃねぇのか。オベロンの放つ闇をいとも簡単に弾いてみせるヴラド。そして弾かれた闇が壊す美宮殿の煌びやかな装飾。それじゃ、こっちからいかせてもらうぜ。現れた棺から生まれる無数の光の竜。さぁ、すべてを喰らい尽くしちまえ。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅱ
聖戦:ふたりの王Ⅱ
♯07 聖戦:ふたりの王ひとりの王が攻撃が繰り出すたびに、美宮殿は悲鳴をあげる。激しい音と共に築かれる瓦礫の山。オレ達の舞台にしちゃ、ちょっともろすぎるんじゃねぇか。すでに失われた宮殿の姿。そして、そんな宮殿の上空でふたりの王は変わらず対峙していた。 -
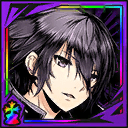 聖戦:ふたりの王Ⅲ
聖戦:ふたりの王Ⅲ
♯08 聖戦:ふたりの王天界の軍勢も、魔界の軍勢も、ただ上空でぶつかり合うふたりの王を見つめていた。いや、見つめることしか出来なかった。少しでも目を離せば、ふたりの姿を見失ってしまう。そう、ふたりの王の戦いは、目で追うだけで精一杯だったのだから。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅲ
聖戦:ふたりの王Ⅲ
♯09 聖戦:ふたりの王かつて、光と闇がぶつかり合ったように、再びぶつかり合う闇と光。どうにか、持ってくれよ。ヴラドが気にかけたのは、仮初の時間。だが、その願いは散る。オベロンの放つ衝撃。それを受け止め切れず、ヴラドの体は地へと打ちつけられたのだった。 -
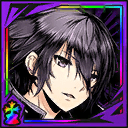 聖戦:ふたりの王Ⅳ
聖戦:ふたりの王Ⅳ
♯10 聖戦:ふたりの王くそっ、こんなときに。それでもすぐに立ち上がるヴラド。そんなヴラドの瞳に飛び込んできたのは、ただ上空のオベロンを見つめる、天界、魔界の両軍勢だった。そして、ヴラドはその眼差しがなにを意味していたのか、すぐに理解したのだった。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅳ
聖戦:ふたりの王Ⅳ
♯11 聖戦:ふたりの王ヴラドを地へと堕とすほどの圧倒的な力。そう、オベロンへ向けられたのは賞賛ではなく、ただの恐怖だった。そして、天界、魔界の両軍勢は同じときに、同じことを想う。互いに協力し、滅ぼすべき相手は、禁忌の血を引くオベロンではないのか、と。 -
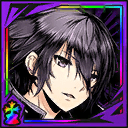 聖戦:ふたりの王Ⅴ
聖戦:ふたりの王Ⅴ
♯12 聖戦:ふたりの王兵の間に伝染する恐怖。そして、各々が構えた武器。向けられた先は、ただひとり上空に浮かぶオベロン。そして、それを止める女王も、参謀長もそこにはいない。誰かが命令を口にすることなく、ただ自然に、オベロンへと向けられていたのだった。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅴ
聖戦:ふたりの王Ⅴ
♯13 聖戦:ふたりの王上空へと放たれた一撃。続くニ撃。止まらない三撃、十撃、百撃。数え切れないほどの刃。炎、水、風、光、闇、無。そのすべてが放たれる。そして、そのすべての攻撃が止んだとき、上空に浮かんでいたのは、そのすべてを受け止めたヴラドだった。 -
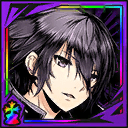 聖戦:ふたりの王Ⅵ
聖戦:ふたりの王Ⅵ
♯14 聖戦:ふたりの王オベロンはただ、傷だらけのヴラドを見つめる。ヴラドはかすみ始めた瞳でオベロンを見つめる。そして、そっと問いかける。どうして避けようとしなかったんだ、と。すると、オベロンはこう答えた。俺は、生まれたときから、世界の敵なんだ、と。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅵ
聖戦:ふたりの王Ⅵ
♯15 聖戦:ふたりの王再び上空へと向けられる無数の刃。だが、吹き抜けたのは突風。ちょっと、道を空けてもらうよ。そして、生まれた一本の道。お疲れさま、は、まだ言わない。だから、行ってらっしゃい。ミドリは、ふたりの小さな女王の背中を見送ったのだった。 -
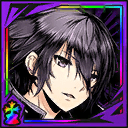 聖戦:ふたりの王Ⅶ
聖戦:ふたりの王Ⅶ
♯16 聖戦:ふたりの王ただ真直ぐに、堂々と胸を張り、ふたりの王の真下へと辿り着いたふたりの女王。誰の許可を得て、王に刃を向けているのかしら。大きく払われた右手。約束を弾いた左手が繋いだ右手。空へと伸びた左手。違うよ、あなたは世界の敵なんかじゃない。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅶ
聖戦:ふたりの王Ⅶ
♯17 聖戦:ふたりの王ふたりの女王の叫び声、静まり返る天界。だが、飾りであるふたりの女王の言葉に耳を傾ける者は多くなかった。少しずつ、少しずつ、また刃が上空へと向けられる。オマエらは、自分らの王のことが信じられないのか。その言葉は再び静けさを呼んだ。 -
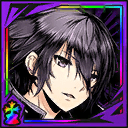 聖戦:ふたりの王Ⅷ
聖戦:ふたりの王Ⅷ
♯18 聖戦:ふたりの王静けさを呼んだ正体、裏古竜衆を引き連れた紅煉帝ヴェルン。聖戦の最終局面、またしても訪れた第三勢力の介入。かつての聖戦の事情を知る者は、口を揃え、予期せぬ邪魔者へ非難の言葉を浴びせるのだった。だが、ヴェルンはその言葉にこう返した。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅷ
聖戦:ふたりの王Ⅷ
♯19 聖戦:ふたりの王邪魔してんのは、いったいどっちだ。そしてヴェルンは天高く掲げた手を、地へと突きつける。揺れる天界、奪われる重心。民共はさっさとひれ伏して、黙って見届けろよ。そして、ふたりの女王の言葉は、しっかりとふたりの王へ届いていたのだった。 -
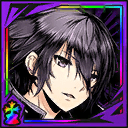 聖戦:ふたりの王Ⅸ
聖戦:ふたりの王Ⅸ
♯20 聖戦:ふたりの王なぁ、聞こえたか。それでも、ただヴラドを見つめ続けるオベロン。あいつら、あの頃のオレ達よりも全然幼いんだぜ、なのに大したもんだよな。小さいながらも、女王であろうとしたふたりの女王。なのにさ、オレ達はいったい、何してんだろうな。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅸ
聖戦:ふたりの王Ⅸ
♯21 聖戦:ふたりの王あの小さな女王はいま、オマエを「守る」選択をした。だったら、オマエがとるべき選択は、あの日のままでいいんだよ。そうさ、このオレと「戦い」、そして勝利すればいいんだ。それは、ヴラドが初めから決めていた「聖戦の結末」だった。 -
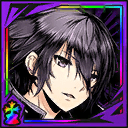 聖戦:ふたりの王Ⅹ
聖戦:ふたりの王Ⅹ
♯22 聖戦:ふたりの王これ、あとで気が向いたら読んでくれ。そしてヴラドは一通の手紙を差し出す。オレからの、降伏文書だ。そして、ヴラドは天界全域に聞こえるよう、声高らかに宣言する。たったいま、この時をもって、オレは天界の王であることを辞めることにした。 -
 聖戦:ふたりの王Ⅹ
聖戦:ふたりの王Ⅹ
♯23 聖戦:ふたりの王続くヴラドの言葉。オマエらはいったい、なにを見て、なにを信じてきた。ざわめき立つ天界の両軍勢。やっぱりオレに、天界は似合わなかったみたいだ。そして、最後の言葉。だってここに、誰よりも天界を愛した、本当の王様がいるんだからな。