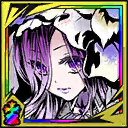パンドラは全てを諦めていた。生きる屍と化した自分に愛など、結婚などという愚かで美しい行為は適さないと。それでも彼女は結婚がしたかった。愛する人と一つに結ばれる契約、そう、ただの契約でしかないその行為を、その証を誰よりも欲していたのであった。魔界の奥深く、一人、誓いの指輪に腰掛けていた。
そっと、ベールはめくられた。待ちわびていた時、覗いたのは、少し伏し目がちな瞳、不安げな表情。ずっと待っていたはずなのに、なぜ涙が溢れるのだろう。嬉しいから、楽しいから、感動したから、そんなありきたりの理由ではなかった。花嫁パンドラは薬指で、体温を、温もりを、生を感じられなかったからだった。
エピメテウスはずっと探していた。神の裁きにより堕とされた最愛の恋人を。もう、何年探し歩いただろうか。それでもまだ辿り着くことの出来ない薬指。彼が手にしていたのは、大切な想いの詰まった一つの箱。いつか、彼女に届けることが出来た時にはきっと。遠のく意識と戦いながら、それでも彼女を探し続けた。
温かな薬指に触れた時、花婿エピメテウスは全てを察した。この温もりこそが愛、そして生きる者全てに与えられた最高の権利。愛すべき者の頬を伝った涙、それは哀しみの涙であり、生きている証でもあった。そして触れたのは自らの頬。そこに涙は流れていなかった。そうか、死んでいたのは、僕の方だったんだね。
堕聖式場<イナーシャ>の端の方、セイカピカリウムは待ちわびていた。自分へ優しくしてくれた花嫁に、最高の聖歌を届けたいと、考えることはそれだけだった。いつ、どこで覚えたのかわからない歌を口ずさむ。それを聖歌だと疑わずに。ただの昔の流行歌かもしれない。それでも歌うことを止めようとはしなかった。
魔物であるにも関わらず、その頭には優しい花冠が乗せられていた。花嫁により乗せられ、そしてフラワヤミリウムと名付けられた生き物は、その手に更なる花びらを集めていた。それは新しい花冠を作ってもらう為ではなく、優しさの恩返しにと、いつか必ず訪れると信じている結婚式の為に集められたものだった。
使い古された誓いの言葉。汝は、良き時も悪き時も、富める時も貧しき時も、病める時も健やかなる時も、共に歩み、他の者に依らず、死が二人を分かつまで、愛を誓い、添うことを、堕聖なる婚姻の契約のもとに、誓いますか。シンプムリウムは来るべき結婚式の為に、何度も何度も繰り返し心の中で読み上げていた。
愛し合う二人は誓った。だが、たった一つだけ、誓うことの出来なかった言葉が。死が二人を分かつまで。そう、既に死により引き裂かれた二人。それでも、二人は愛を誓った。例え、愛する人が死のうと、二度と会えなくなろうと、それでもそこには、確かに愛は存在する。シンプムムリウムはそんな二人を見送った。
光の花嫁は、闇の花婿をずっと、ずっと、待っていた。闇の花婿は、光の花嫁をずっと、ずっと、探していた。神の裁きにより引き裂かれた二人は、再び出会い、そして堕聖の愛を誓うことが出来るのだろうか。誓いの指輪はまだ、輝き続けていた。
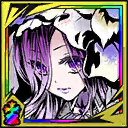 堕聖式場イナーシャ
堕聖式場イナーシャ