STORIES 2017年4月26日のストーリー
この日に実装されたストーリーの一覧です。
-
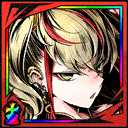 扉の先へ:古の竜Ⅴ
扉の先へ:古の竜Ⅴ
♯21 扉の先へ:古の竜あなたのよく知る、あの子だよ。ドロシーたちの背中へ近づく足音。まさか、あの子っていうのは……。ハムの瞳には近づく足音の正体が映し出されていた。そして、その正体の手には、一冊の分厚い本が握られていた。辿り着いたっていうの……!? -
 扉の先へ:古の竜Ⅴ
扉の先へ:古の竜Ⅴ
♯22 扉の先へ:古の竜それじゃあ、先に行ってるね。ドロシーはその足音の正体を確認することなく、奥へと歩き始めた。そして、足音の正体はハムの正面で立ち止まる。久しぶりね。言葉を発した足音の正体。やっぱり、私に会いたくなかったのかしら。ねぇ、お母さん。 -
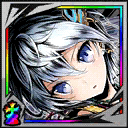 扉の先へ:古の竜Ⅴ
扉の先へ:古の竜Ⅴ
♯23 扉の先へ:古の竜何年ぶりだろうか、何十年ぶりだろうか、何百年ぶりだろうか。果たされた再会。大きくなったじゃない。顔をあげたハム、瞳に映し出されたカナン。この竜界に、あなたの居場所はない。だけど、居場所は作れるの。それを、あの人は教えてくれた。 -
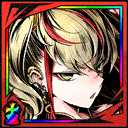 扉の先へ:古の竜Ⅴ
扉の先へ:古の竜Ⅴ
♯24 扉の先へ:古の竜それじゃあ、行ってくるね。ハムへと向けられたお別れの言葉。決して振り返ることのないカナン。そして、カナンを呼び止めることの出来ないハム。そう、ハムはただ下を向き、後悔の涙を流していたから。それもまた、ひとつの家族の形だった。 -
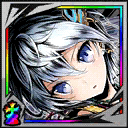 扉の先へ:古の竜Ⅴ
扉の先へ:古の竜Ⅴ
♯25 扉の先へ:古の竜お待たせ。ドロシーたちの横に並んだカナン。ドロシーはブリキに抱えられ、少し高い位置からありがとうを伝えた。ううん、お礼を言うのは私のほう。私じゃ、最奥を見つけることは出来なかった。そんなふたりの瞳には、希望だけが満ち溢れていた。 -
 扉の先へ:古の竜Ⅵ
扉の先へ:古の竜Ⅵ
♯26 扉の先へ:古の竜さぁ、到着だよ。祠の最深部、岩のくぼみには、枯れることのない最古の竜の血が。これでやっと、もう一度会えるんだ。目を輝かせていたドロシー。その前に、ワタシからお話をさせてもらってもいいかな。やけに真剣な声は、ボームのものだった。 -
 扉の先へ:古の竜Ⅵ
扉の先へ:古の竜Ⅵ
♯27 扉の先へ:古の竜彼を再び綴ったとしても、それは彼の物語の続きでしかない。その言葉がいったいなにを意味しているのか。そう、彼には綴られし者という、逃れることの出来ない運命が待っている。そんな過酷な運命に、彼を再び呼び戻しても、本当にいいのかな。 -
 扉の先へ:古の竜Ⅵ
扉の先へ:古の竜Ⅵ
♯28 扉の先へ:古の竜ボームは知っていた。この先、オズに与えられるべき運命の結末を。彼の命を握っているのはワタシじゃない。アイツの気分ひとつで、彼の結末は訪れてしまう。命は失われてしまうんだ。だからアイツは、彼を生かし続けた。いつでも殺せるんだから。 -
 扉の先へ:古の竜Ⅵ
扉の先へ:古の竜Ⅵ
♯29 扉の先へ:古の竜それなら、答えは簡単じゃない。自信満々の笑みを浮かべたドロシー。って、それは私の言葉じゃないか。そう言いながら見つめた先にいたのはカナン。約束する、そんな運命、私が壊してみせるって。そして、カナンは一足先にその場を後にした。 -
 扉の先へ:古の竜Ⅵ
扉の先へ:古の竜Ⅵ
♯30 扉の先へ:古の竜やっぱ、会うのは照れくさかったのかな。カナンを見送ったドロシー。それじゃあ、始めるよ。筆を手にしたボーム。書に綴られた文字は踊りだし、すべての文字が炎に包まれる。その炎が落とした竜の影。ドロシーの瞳に溜まった涙。…お帰りなさい!