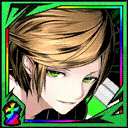STORIES 2016年9月14日のストーリー
この日に実装されたストーリーの一覧です。
-
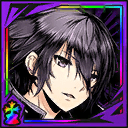 聖戦:回想・オベロン09
聖戦:回想・オベロン09
♯25 聖戦:回想ひとり生き残ったオベロンに生気は残されていない。そして、されるがままにされた幽閉。こうして、いったい何年の月日が流れただろうか。再び聖なる扉が開かれたとき、ひとりの人間が天界の裏側、深い闇が閉じ込められた洞窟へと迷い込んでいた。 -
 聖戦:回想・ヒスイ09
聖戦:回想・ヒスイ09
♯26 聖戦:回想聖なる扉は閉じられ、天界と魔界の連絡手段は限られていた。ヒスイは調停役というその任から解放された。終わった戦いを掘り返すつもりはない。だが、出来ることなら、もう一度ふたりに、ふたりが目指せたはずの道を歩かせたいと願っていた。 -
 聖戦:回想・ヴラド09
聖戦:回想・ヴラド09
♯27 聖戦:回想目を開けようが、閉じようが、ヴラドの目の前には暗闇が広がっていた。ヴラドは負けを認めていた。だが、ヴラドは気づいていたのだった。最後の一刺しが、オベロンのものではなかったこと。そして、オベロンが王の涙を流し続けていたことを。 -
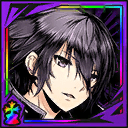 聖戦:回想・オベロン10
聖戦:回想・オベロン10
♯28 聖戦:回想朽ちていた牢獄の鍵。人間の女はオベロンの元へと通い続けた。会話を続けた。元の世界には大切な家族がいたことを。家族という存在の大切さを。そして、次第に開かれるオベロンの心。そんなふたりの間に、新しい家族の命が宿ったのだった。 -
 聖戦:回想・ヒスイ10
聖戦:回想・ヒスイ10
♯29 聖戦:回想幽閉されたオベロン。棺で眠るヴラド。自分だけが普通に生きていいのだろうか。ヒスイはあの日の自分を責めるかのように、竜王家を抜け、ひとりであの日の続きを探していた。そして再び聖なる扉が開かれたとき、かすかな希望を抱いたのだった。 -
 聖戦:回想・ヴラド10
聖戦:回想・ヴラド10
♯30 聖戦:回想禁忌の間で、身動きひとつとれず、無限とも思われる時間を過ごしていたヴラド。だが、そんなヴラドの耳に入ってきた思わぬ言葉。生まれてしまった禁忌の子。なんだよ、元気にしてんじゃねぇか。それは共に禁忌を犯したもうひとりの王への祝福。