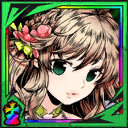STORIES 11月19日
この日に実装されたストーリーです。
-
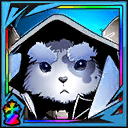 家族の絆Ⅱ
家族の絆Ⅱ
♯02 家族の絆季節が変わるたびに用意されていた洋服。そして、そんな洋服が用意されなくなってから、いったいどれだけの季節が流れただろうか。常界に近づいてきたのは雪降る季節の足音。トトの寝床には、誰かの匂いの染み付いた洋服が敷き詰められていた。
2013/11/19
この日に実装されたストーリーはありません
2014/11/19
この日に実装されたストーリーはありません